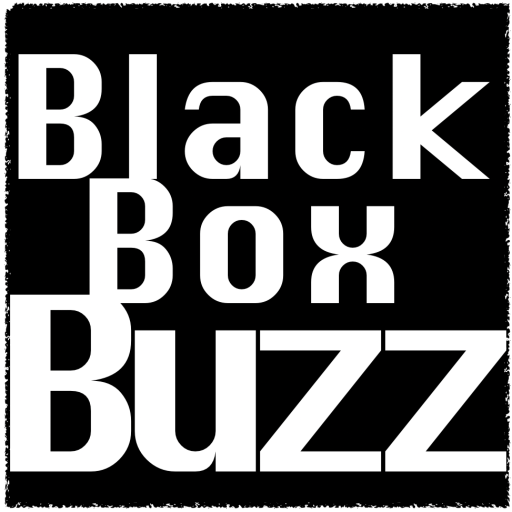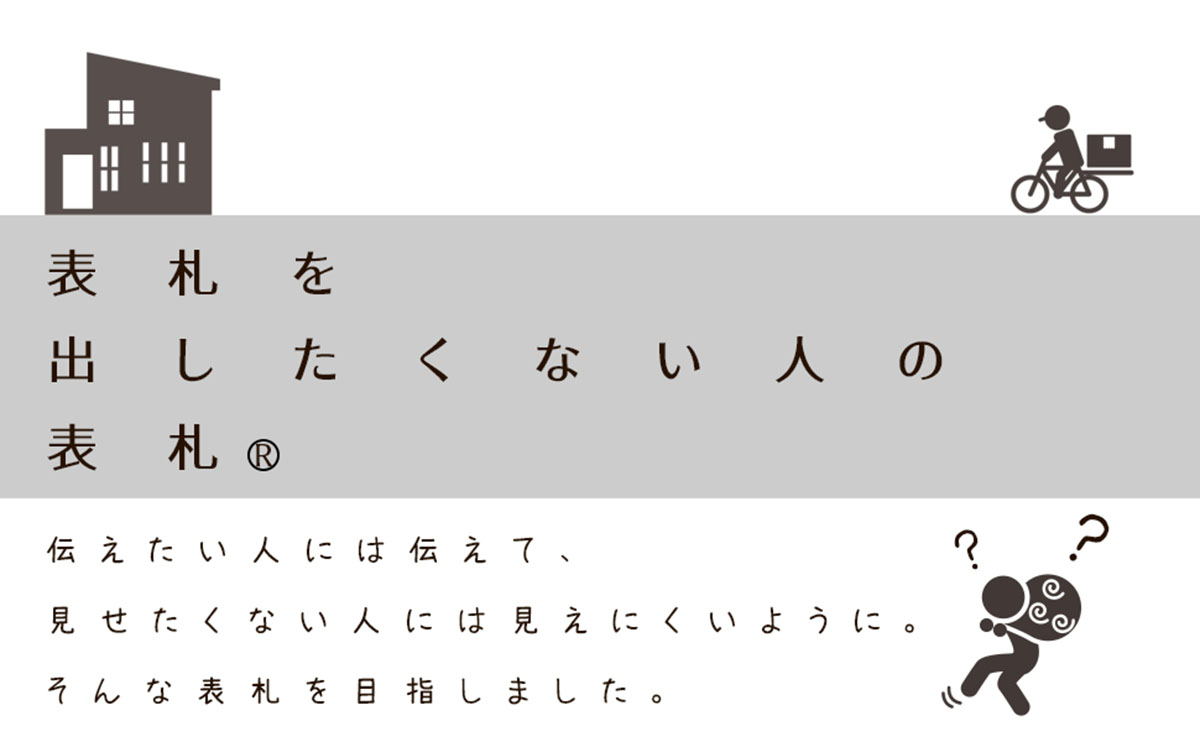[ 表札を出したくない人の表札 「 WATANABE 」 【 渡辺 】 本物の真鍮で作ったサインプレート ]
「忘れられた瓶」
夜の静けさが街を包み込むころ、渡辺さんはいつものように小さな居酒屋で一杯の酒を楽しんでいた。この店は、彼が日々の疲れを癒すための隠れ家だった。店内は常連客が集う温かい雰囲気で、渡辺さんもその一人だった。
しかし、その夜は少し様子が違った。カウンターの端に座っている見慣れない女性がいた。彼女は黒いコートに身を包み、深く帽子をかぶっていたため、顔はほとんど見えなかった。ただ、その姿にはどこか不思議な魅力があり、渡辺さんは思わず彼女に目を留めた。
「初めて見る顔だな…」
彼はそう思いながらも、声をかけるのは控えた。なぜなら、その女性が近寄りがたい雰囲気をまとっていたからだ。
店のマスターが彼女に話しかける。
「いらっしゃい。何を飲まれますか?」
女性は一瞬、沈黙した後、かすかな声で答えた。
「…あの、何年も前にここに置いてもらった瓶があるはずなんです。それをください。」
渡辺さんは驚いた。こんな小さな店で、しかも何年も前に置いた酒があるなんて、聞いたことがない。マスターも戸惑った様子で、店の奥に消えた。
数分後、マスターは古びた瓶を持って戻ってきた。その瓶は、まるで時が止まっているかのように、埃をかぶっていた。渡辺さんは息を呑んだ。どうしてそんなものがここに残っているのか。
「こちらでよろしいですか?」マスターが尋ねると、女性は静かに頷き、瓶を手に取った。
「ありがとう。この酒を、もう一度味わうことができて良かった…。」
その言葉を最後に、女性は瓶を持って立ち上がり、店を後にした。
渡辺さんは、不思議な感覚に包まれた。彼女の背中を見送るうちに、どうしても一つの質問が浮かんできた。
「彼女は一体誰だったんだ?」
マスターに尋ねてみたが、答えは意外なものだった。
「さあな。ただ…あの瓶を置いていったのは、確か20年前だよ。」
渡辺さんは凍りついた。20年前?その時、彼は気づいた。女性が最後に座っていた椅子が、冷たく濡れていることに。まるで、そこに座っていたのが…生きた人間ではなかったかのように。
その夜以来、渡辺さんはその居酒屋に通うたび、あの瓶がまた置かれているかどうかを確かめずにはいられなかった。しかし、二度とその瓶を見ることはなかった。